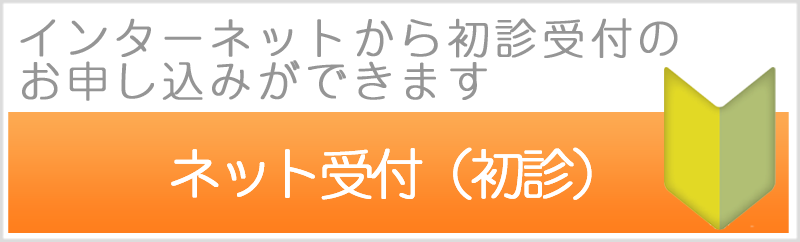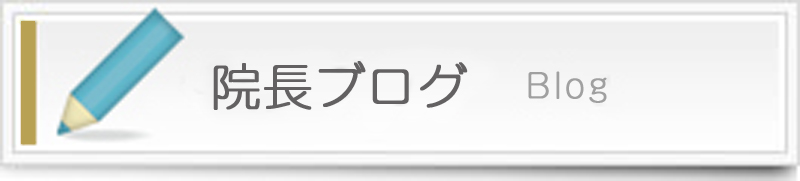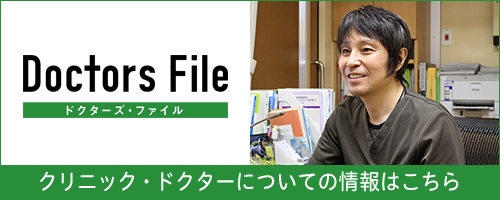院長ブログ
高血圧治療と新型コロナウイルス感染症
現在も新型コロナウイルス感染が流行しています。
当院では高血圧を治療中の患者様がたくさんいらっしゃいますが
今回横浜市立大より興味深い報告があったのでご報告いたします。
新型コロナウイルスは、アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)受容体を介して
細胞に侵入することが明らかになっており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と
レニン-アンジオテンシン系(RAS)との関連が注目されています。
今回、横浜市立大学附属 市民総合医療センター 心臓血管センターの
松澤 泰志氏らの研究グループが、COVID-19罹患前からのACE阻害薬または
ARBの服用と重症度との関係について、多施設共同後ろ向きコホート研究
(Kanagawa RASI COVID-19 研究)を行ったと報告されました。
Hypertension Research誌オンライン版2020年8月21日号での報告です。
本研究では、2020年2月1日~5月1日の期間、神奈川県内の6医療機関
(横浜市立大学附属市民総合医療センター、神奈川県立循環器呼吸器病センター、
藤沢市民病院、神奈川県立足柄上病院、横須賀市立市民病院、横浜市立大学附属病院)に
入院したCOVID-19患者151例を対象に、病態に影響を与える背景や要因の解析が行われました。
追跡調査の最終日は2020年5月20日で、すべてのデータは
医療記録から遡及的に収集されました。
高血圧症およびほかの既往歴の情報は、通院歴、入院時の投薬、および
ほかの医療機関からの提供内容に基づいています。
主な結果は以下のとおり。
・平均年齢は60±19歳で、患者の59.6%が男性でした。
151例のうち、39例(25.8%)が高血圧症、31例(20.5%)が糖尿病、
22例(14.6%)にACE阻害薬またはARBが処方されていました
(ACE阻害薬:3例[2.0%]、ARB:19例[12.6%])。
・151例中、14例(9.3%)の院内死があり、14例(9.3%)で人工呼吸、
58例(38.4%)で酸素療法が必要だった。
入院時、肺炎に関連する意識障害は14例(9.3%)、
収縮期血圧<90mmHgに関連する意識障害は3例(2.0%)で観察され、
少なくとも13例において、新型コロナウイルス感染が原因とされた。
22例(14.6%)がICUに入院した。
・患者全体を対象とした単変量解析では、65歳以上
(オッズ比[OR]:6.65、95%信頼区間[CI]:3.18~14.76、p<0.001)、
心血管疾患既往(OR:5.25、95%CI:1.16~36.71、p=0.031)、
糖尿病(OR:3.92、95%CI:1.74~9.27、p<0.001)、
高血圧症(OR:3.16、95%CI:1.50~6.82、p=0.002)が、
酸素療法以上の治療を要する重症肺炎と関連していました。
・多変量解析では、高齢(65歳以上)が重症肺炎と関連する独立した要因だった。
(OR:5.82、95%CI:2.51~14.30、p<0.001)。
・高血圧症患者を対象とした解析の結果、
ACE阻害薬またはARBをCOVID-19罹患前から服用している患者では、
服用していなかった患者よりも、主要評価項目の複合アウトカム
(院内死亡、ECMO使用、人工呼吸器使用、ICU入室)
における頻度が少ない傾向だった(14.3%vs.27.8%、p=0.30)。
また、副次評価項目については、COVID-19に関連する意識障害が有意に少なかった
(4.8%vs.27.8%、p=0.047)。
著者は「われわれの知る限りでは、これがわが国で初めてCOVID-19患者の
臨床アウトカムを検討した研究だ。
今回、炎症に対するRAS阻害薬の保護効果が、ACE阻害薬/ARBの使用と
意識障害の発生減少を関連させる1つのメカニズムである可能性が明らかになった」と記しています。
参考:ケアネット
当院では高血圧でACE阻害剤やARBで治療中の患者さんが非常に多く
服薬メリットについても説明を行っています。
まだまだ新型コロナウイルスの感染が収束しないなか
今後もさらなる研究結果が期待されるところです。
新型コロナウイルスと生活習慣病
現在、新型コロナウイルスの感染の第2波だといわれています。
8/24に厚生労働省に助言する新型コロナ専門家の会合が行なわれました。
これまでに亡くなった人や重症になった人たちの分析などが報告されました。
第1波の流行と比べて現在の流行では、亡くなった人の数は少ないものの
高齢の人の致死率はほとんど変わっていないということです。
8月24日開かれた会合では、現在の感染状況について流行はピークに達してはいるものの、
このあと減少するかどうかは現時点では分からず、感染の再拡大への警戒が必要な状況だと評価しました。
また、国立感染症研究所から、第1波の流行と現在の第2波の流行のそれぞれの致死率が報告されました。
その結果、ことし5月までの第1波の際の致死率は6%だったのに対し、
6月以降は4.7%と低下傾向になっていました。
ただ年代別に見てみますと、50代、60代の致死率は第1波が2.8%、第2波が3.1%。
また70代以上の致死率は、第1波の際が25.1%、第2波が25.9%とほとんど変わっていなかったということです。
また、ことし3月までの516人分の患者データから人工呼吸器を装着したり、
死亡したりするリスクと関係のある要因を分析したところ、
男性は女性に比べてリスクが2.8倍になっていたほか、
基礎疾患については
▽高尿酸血症が3.2倍
▽慢性肺疾患が2.7倍
▽糖尿病が2.5倍
▽脂質異常症が2.1倍 になっていたということが報告されました。
もともと糖尿病、高血圧や慢性肺疾患のコロナ感染症の重症化の報告はこれまでにも
あったのですが、今回、高尿酸血症の重症化率が肺疾患よりも高かったとの報告には
我々医療者も正直驚いています。
高尿酸血症は、動脈硬化性疾患との関係は現在では常識となっていますが
感染症との関係は報告がなく、これからの解析などが期待されます。
当院では上記疾患のような生活習慣病に常に力を入れ診療を行なっています。
そのような方は全力でサポートしてまいりますのでいつでもご相談ください。
新規睡眠導入剤 デエビゴ
現在、世界中で、新型コロナウイルス(COVID19)の感染症が世界中で
蔓延しています。
わが国も政府が行ってきた独自の感染対策にて何とか第1波を封じ込めようとしています。
当院でも様々な感染対策を講じておりますが、
皆様も手洗い、うがいなど常に心がけるようにいたしましょう。
ところで、当院では、循環器疾患、生活習慣病である高血圧、
糖尿病や脂質異常症に加え、睡眠時無呼吸症候群に関連する不眠症
などにも注力し、診療を行ってきております。
睡眠障害は睡眠時無呼吸症候群に代表される内科的疾患の
除外が大切です。
当院ではしっかりと問診を行い、必要であれば内科的疾患の除外を行ったうえで
睡眠障害の治療を行います。
睡眠障害は、床に入ってもなかなか寝付けない入眠障害、
夜中に何度も覚醒する中途覚醒、朝早く目が覚めてしまう
早朝覚醒などに分類されます。
わが国に限らず、古くからハルシオンやデパスなどに代表される
ベンゾジアゾピン系薬に代表される不眠症治療薬が用いられてきました。
しかし、以前当ブログでもお伝えいたしましたように2014年に
新規睡眠導入剤ベルソムラ(スポレキサント)が発売になりました。
当薬剤はオレキシンの受容体への結合をブロックすることで、
過剰な覚醒状態を抑制し、脳を覚醒状態から睡眠状態へと
移行させるという生理的なプロセスをもたらす世界初のオレキシン受容体拮抗薬でした。
しかし、どうしても従来のハルシオンなどに代表されるベンゾジアゾピン系薬
に比してどうしても効果が弱いことが言われてきました。
しかし、今回発売されるデエビゴ錠(レンボレキサント)は
海外の国際共同第3相プラセボ/ゾルピデムER対照比較試験でも
プラセボ、ゾルピデムER(日本では未発売のマイスリーER錠)ともに
有意差をもって入眠、中途覚醒ともに改善したとの結果が報告されています。
すなわち、従来の認知症になりにくいといわれるオレキシン受容体拮抗薬の中でも
かなり期待が持てるといえます。
睡眠障害は高血圧や糖尿病につながる大事な疾患といえます。
しかし、睡眠導入剤で認知症リスクが上がるのでは意味がないといえると思いますが、
デエビゴ錠は認知症が急増しているの我が国の睡眠治療剤として期待できる
薬剤ではないかと考えています。
当院でもすでに同薬剤の勉強会を開催し、今後の不眠治療に導入する予定です。
もし、デエビゴ錠についての質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
高血圧ガイドライン 2019
日本高血圧学会は、5年ぶりに改訂となる「高血圧治療ガイドライン2019)」を発表しました。

新しいガイドラインで示された高血圧の基準値は従来通り、
診察室血圧が140/90mmHgで、家庭血圧が135/85mmHgとなっています。
正常高値血圧(120~129/80mmHg未満)以上のすべての者は、生活習慣の修正が必要で、
高リスクの高値血圧および高血圧(140/90mmHg以上)では、生活習慣の修正を積極的に行い、
必要に応じて降圧薬治療を開始することが推奨されました。
(いずれも診察室血圧)
降圧目標は、診察室血圧が130/80mmHgで、家庭血圧が125/75mmHgとなっています。
糖尿病患者、腎臓病患者(蛋白尿陽性)、抗血栓薬服用中の患者などの降圧目標も、
従来通り130/80mmHg未満(家庭血圧は125/75mmHg未満)になりました。
ただし、75歳以上の降圧目標は140/90mmHg未満とより強化され、
さらに併存疾患などによって降圧目標が130/80mmHg未満とされる場合、
75歳以上でも忍容性があれば個別に判断して
130/80mmHg未満への降圧を目指すこととなっています。
「NIPPON DATA 2010」などの調査によると、日本の高血圧有病者数は
4,300万人に上るといわれますが、うち57%(2,450万人)しか治療を受けていないとされます。
さらに、治療を受けている患者の50%(1,200万人)しか
血圧が基準である140/90mmHg未満にコントロールされていないとされています。
高血圧対策を実効を上げるために、われわれ医療機関(かかりつけ医、看護師など)、
保健師、管理栄養士、薬剤師、地域の行政機関、地域の産業界などが、
密接に連携・協働する必要があるのです。
地域での高血圧診療でもっとも重要なのは、患者さん・家族と医療チームが十分な
パートナーシップを築き、降圧目標に到達するための具体的な治療計画を設定し
共有することだといわれています。
とにかく塩分摂取制限は基本中の基本です。
当院では高血圧患者さんには食事指導を徹底して行っておりますが、
食事・運動療法で血圧コントロール困難な患者さんには
薬物治療を納得して行うようこれからも心がけていきたいと思います。
なんでもお気軽にご相談ください。
新規抗インフルエンザ薬 ゾフルーザ
いよいよインフルエンザの季節となってきました。
インフルエンザの治療薬に今年3月に塩野義製薬から1回飲みきりの新薬
ゾフルーザ錠が発売になりました。
当院でもいち早く導入し、現在までに処方を行ってきております。
ゾフルーザは、これまでのインフルエンザ治療薬(タミフル、リレンザ〔一般名:ザナミビル〕、
イナビル〔一般名:ラニナミビル〕、ラピアクタ〔一般名:ペラミビル〕)とどう違うのでしょうか?
まず作用機序(メカニズム)が、これまでの薬と全く違います。
これまでのインフルエンザ治療薬は、ノイラミニダーゼ阻害薬と
呼ばれる種類の薬で、感染した人の細胞の中で増殖したインフルエンザウイルスが、
他の細胞に広がるのを抑える作用がありました。
一方、ゾフルーザには、ウイルスの増殖そのものを抑える働きがあります。
ゾフルーザの効果は非常に高いといえます。
インフルエンザを発症した後、熱や咳、鼻水、節々の痛み、疲労感などの
症状がすべてなくなるまでの時間(罹病期間)についていうと、
ゾフルーザはプラセボ(偽薬)より中央値で1日余り早く、
タミフルとの比較では同等という結果が出ています。
罹病期間ではタミフルとの差が出ていませんが、ゾフルーザはインフルエンザの主症状である
『きつい、つらい』症状に関して、従来の薬よりも『早く楽になった』と話す患者さんが多い印象です。
その理由として作用機序の違いが考えられています。
ゾフルーザには、インフルエンザウイルスの増殖そのものを抑える作用があるので、
ウイルスがなくなるスピードが速いのです。
ゾフルーザを投与すると、丸一日で半分の人のウイルスがなくなります。
これまでの薬の中で最もウイルスの消失が早いラピアクタでも、
3日で80%の人のウイルスがなくなる程度ですから、かなり早いスピードです。
患者さんの中には、昼に当院を受診してゾフルーザの処方を受け、
翌朝には『楽になりました』と話す人もいます。
ただ、今後タミフルのように耐性株が増えるとの予測もあり、
吸入薬も適正に使用していかねばなりません。
もうすぐインフルエンザの本格的な流行シーズンを迎えます。
当院では高齢者で、心不全などの心疾患や糖尿病、高血圧や肺気腫など
様々な基礎疾患をお持ちの方がおりますので、インフルエンザの予防はもちろん
罹患した時の速やかな検査、適切な治療を行っていくことに全力を尽くしたいと思います。
診療内容
くわはたクリニック
所在地
〒892-0811鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目5-1
お問い合わせ
TEL:099-220-9502FAX:099-220-9503
アクセス
◆バス 玉里団地中央バス停より徒歩3分◆その他 スーパータイヨー玉里団地店前