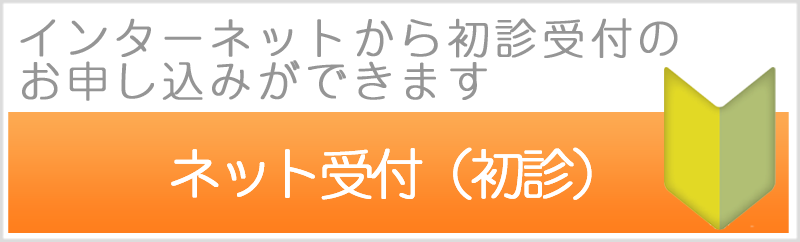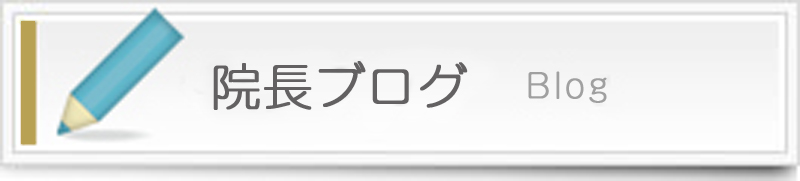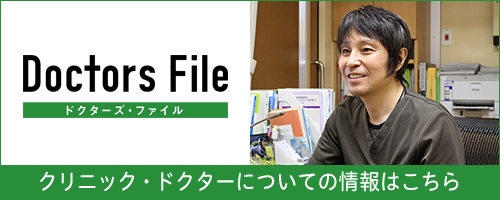院長ブログ
2024-04-10
当法人はグループホームを運営しています。
認知症と診断されている患者様などが27人共同で生活されており、
当院より訪問診療などを行って医学的管理も行っています。
ご高齢の患者様が多く、どうしても高齢になると食欲の低下などが課題となってきます。
先日、介護スタッフ主催で当院の駐車場でのバーベキュー大会が開催されました。
当日は雨天も心配されましたが、なんとか開催できました。
普段は寝たきりの患者様も車いすを利用し、ほとんどの患者様にご参加いただきました。
職員が準備した焼きそばやおにぎり、そして炭火での焼肉を患者様に
召し上がっていただきました。
そこで感じたことですが、普段は流動食でなかなか食が進まない患者様もおられるのですが、
その日は焼きそばなど(患者様向けに肉などもやわらかく調理しています)を
モリモリと食べられていることに驚きを隠せませんでした。
人は環境により食欲が刺激されるとの研究は多数の報告がありますが、
まさしくそうだなと痛感した次第でした。
当施設でもこれからもこのような取り組みを継続して行っていこうと思った次第です。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajscs/20/0/20_0_94/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajscs/20/0/20_0_94/_article/-char/ja/
2024-02-21
当院には高血圧で通院されている患者さまが数多くいらっしゃいます。
血圧については大原則なのは減塩なのですが、最近の研究では有酸素運動の重要性が次々と報告されています。
コネチカット大学より報告された高血圧とウォーキングによる効果の論文をご紹介いたします。
高血圧のある高齢者は、1日の歩数を3,000歩増やすと、血圧を大幅に低下できることが明らかになりました。
米国の高齢者の80%は高血圧と推定されている。血圧値を正常に管理することで、心不全・心臓病・脳卒中・腎臓病などの
深刻な病気のリスクを減らすことができるとのことです。 「歩数を3,000歩増やすと、多くの高齢者は1日の歩数は7,000歩となり、
運動ガイドラインで推奨された運動量をみたすことができます。
1日の歩数を3000歩増やすと高血圧を大幅に軽減できる
高血圧のある高齢者は、1日の歩数を3,000歩増やすと、血圧を大幅に低下できることが明らかになりました。
ウォーキングは、誰でも、いつでも、どこでも取り組める運動として人気が高いです。
「米国の高齢者の80%は高血圧と推定されています。血圧値を正常に管理することで、
心不全・心臓病・脳卒中・腎臓病などの深刻な病気のリスクを減らすことができます。
ご高齢の方は、1日の歩数を3,000歩増やすと、高血圧を大幅に軽減できることが分かりました。
これは、個人差はありますが、1日30分のウォーキングに相当します。
最小限の運動介入で効果をえられるのです。
脳卒中リスクを36%減少するのに相当
研究は、高血圧があり、1日に座ったまま過ごす時間が長い、年齢が73歳(中央値)の高齢者21人(男性8人、女性13人)を対象に実施したもの。
参加した高齢者の年齢は68歳~78歳で、1日の歩数は平均して約4,000歩でした。 その結果、歩数を3,000歩程度増やし、
1日に7,000歩にすると、参加者の収縮期(最高)血圧は平均7ポイント、拡張期(最低)血圧は平均4ポイント、それぞれ低下したとされます。
これは、全死因による死亡の相対リスクが11%減少し、心血管死亡のリスクは16%減少、心臓病のリスクは18%減少、
脳卒中のリスクは36%減少するのに相当するとされています。 参加者には、歩数計、血圧計、毎日どれだけ歩いたかを記録する
日記などのキットが与えられました。
1日に3000歩増やすのは難しくない
これまでの研究でも、運動が高血圧のある成人の血圧値を即時的かつ長期的に下げるのに効果的であることが示されています。
「年齢を重ねて、長生きすると、ほとんどの人は血圧値が高くなります。ウォーキングは誰でも簡単に取り組め、特別な道具は必要なく、
いつでもどこでも行うことができるのです。 「歩数を3,000歩増やすと、多くの高齢者は1日の歩数は7,000歩となり、
運動ガイドラインで推奨された運動量をみたすことができます。1日に3,000歩増やすことは、難しいことではないのです。
米国の運動ガイドラインでは、活発な運動や身体活動を、週に150分行うことが推奨されています。
高齢者が、毎日の歩数を1日あたり3,000歩増やすと、その運動量を満たすことができるとされています。
運動には降圧薬と同等の効果が
降圧薬などを服用している人でも、運動療法と薬物療法を組み合わせることで、治療効果をさらに増強できる可能性があるというのです。
「高齢者が運動に取り組むと、降圧薬と同等の血圧管理をえられることも分かりました。参加者のうち8人は降圧薬を服用していましたが、
毎日の歩数を増やすことで、やはり収縮期血圧の改善がみられましたというのです。
「生活スタイルのシンプルな介入により、体系的な運動指導や、薬物療法と同じくらいの効果をえることが可能であることが
示されたのは興味深いです」としている。 なお、歩行速度や歩行を継続して行うことは、単純に歩数を増やすことに比べて、
それほど重要ではないことも分かりました。 「この場合で重要なのは、運動や身体活動の強度ではなく、
その量であることが示されました。歩数を増やすことを目標にすると、健康上のベネフィットをえられるとされています。
今回の研究はパイロット研究であり、研究グループはえられたデータを使用し、より大規模な臨床試験を実施することを計画しているといいます。
Increasing Steps by 3,000 Per Day Can Lower Blood Pressure in Older Adults (コネチカット大学 2023年9月26日)
Increasing Lifestyle Walking by 3000 Steps per Day Reduces Blood Pressure in Sedentary Older Adults with Hypertension:
Results from an e-Health Pilot Study (Journal of Cardiovascular Development and Disease 2023年7月27日)
Increasing Lifestyle Walking by 3000 Steps per Day Reduces Blood Pressure in Sedentary Older Adults with Hypertension:
Results from an e-Health Pilot Study (BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023年7月27日)
当院では高血圧の患者様には丁寧に疾患についてや、治療法につきまして説明を行っております。
気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
2022-12-23
当院は生活習慣病、特に動脈硬化性疾患の診療に特に注力しております。
今回は5年ぶりに改訂され7月4日に発刊された動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版について
解説を行いたいと思います。
今回の改訂でキーワードとなるのが、「トリグリセライド(中性脂肪、以下TG)」「アテローム血栓性脳梗塞」「糖尿病」です。
<2022年度版の主な改訂点>
1)随時(非空腹時)のトリグリセライド(TG)の基準値を設定。
2)脂質管理目標値設定のための動脈硬化性疾患の絶対リスク評価手法として、
冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞を合わせた動脈硬化性疾患をエンドポイントとした久山町研究のスコアが採用。
3)糖尿病がある場合のLDLコレステロール(LDL-C)の管理目標値について、末梢動脈疾患、
細小血管症(網膜症、腎症、神経障害)合併時、または喫煙ありの場合は100mg/dL未満とし、
これらを伴わない場合は従前どおり120mg/dL未満とした。
4)二次予防の対象として冠動脈疾患に加えてアテローム血栓症脳梗塞も追加し、LDL-Cの目標値は100mg/dL未満とした。
さらに二次予防の中で、「急性冠症候群」「家族性高コレステロール血症」「糖尿病」
「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞の合併」の場合は、LDL-Cの管理目標値は70mg/dL未満とした。
5)近年の研究成果や臨床現場からの要望を踏まえて、新たに下記の項目を掲載。
(1)脂質異常症の検査
(2)潜在性動脈硬化(頸動脈超音波検査の内膜中膜複合体や脈波伝播速度、
CAVI:Cardio Ankle Vascular Indexなどの現状での意義付)
(3)非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
(4)生活習慣の改善に飲酒の項を追加
(5)健康行動倫理に基づく保健指導
(6)慢性腎臓病(CKD)のリスク管理
(7)続発性脂質異常症
変更に至った主な理由
1)について、「TGは食事の摂取後は値が上昇するなど変動が大きい。また空腹時でも非空腹時でも値が高いと
将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡を予測することが国内の疫学調査で示されている。
国内の疫学研究の結果およびESC/EASガイドラインとの整合性も考慮して、
空腹時採血:150mg/dL以上または随時採血:175mg/dL以上を高TG血症と診断する」とコメントされています。
2)については、吹田スコアに代わり今回では久山町研究のスコアを採用。その理由として、
「吹田スコアの場合、研究アウトカムが心筋梗塞を含む冠動脈疾患発症で脳卒中が含まれていなかった。
久山町研究のスコアは、虚血性心疾患と、脳梗塞の中でとくにLDL-Cとの関連が強い
アテローム血栓性脳梗塞の発症にフォーカスされていた点が大きい」と説明。
3)については、ESC/EASガイドラインでの目標値、国内のEMPATHY試験やJ-DOIT3試験の報告を踏まえ、
心血管イベントリスクを有する糖尿病患者の一次予防において、十分な根拠が整っている。
4)については、国内でのアテローム血栓性脳梗塞が増加傾向であり、再発予防が重要になるためである。
また二次予防の場合、糖尿病の合併がプラーク退縮の阻害要因となることなどから
「これまで厳格なコントロールは合併症などがあるハイリスクの糖尿病のみが対象だったが、
今回より糖尿病全般においてLDL-C 70mg/dL未満となった」と解説されています。
5)の(7)続発性脂質異常症は新たに追加され、他疾患などが原因で起こる続発性なものへの注意喚起として
「続発性(二次性)脂質異常症に対しては、原疾患の治療を十分に行う」とし、甲状腺機能低下症など、
続発性脂質異常症の鑑別を行わずに、安易にスタチンなどによる脂質異常症の治療を開始すると
横紋筋融解症などの重大な有害事象につながることもあるので注意が必要、と記載されています。
当院では脂質異常症の患者さんがたくさんおられますが
ガイドラインは当然のことながら、画像診断も組み合わせ、患者さんの最適な治療になるよう
常に努めております。
脂質異常症のセカンドオピニオンも受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
2022-01-13
現在、新型コロナウイルス感染の第6波に突入したといわれております。
病原性は低下しているものの感染力はデルタより、
より強力なオミクロン株が流行しているといわれています。
- 新型コロナ感染症かすぐ知りたい
- 新型コロナ感染症かどうか正確に判断してほしい
そのような方のために当院ではIDNOW™による新型コロナ感染症遺伝子検査を導入いたしました。
今回は遺伝子検査の特徴と精度などについて解説していきます。
IDNOW™による新型コロナ感染症遺伝子検査とは
 (Abbot社HPより転載)
(Abbot社HPより転載)
IDNOW™による新型コロナ感染症遺伝子検査とは「新型コロナの遺伝子(RNA)を抽出・増幅することで、
新型コロナかどうかを判定する」検査です。従来、新型コロナかどうかを判定する検査方法として
広く知られているものに「PCR検査」や「抗原検査」がありますが、今回の遺伝子検査は
等温核酸増幅法の1つである NEAR法 (Nicking Enzyme Amplification Reaction)となります。
NEAR法の特徴としては、以下の通りです。
- PCRと同じ「核酸検出検査」に該当する:10日以降の症状がある方の陰性証明にも
使用することができ、ガイドライン上でもPCRと同等の信頼性を持っているのが特徴です。
- (参照:COVID-19病原体検査の指針による)
- 非常に判定までがスピーディー: 検査自体は陽性に最短5分、陰性でも13分で判定することができます。
- (操作に追加で時間がかかりますので、複数人される場合は結果を電話連絡させていただく場合があります)
- 海外渡航の陰性証明にも使用されている:検査の信頼性から、アメリカ(ハワイ含む)や
韓国などの渡航の際にIDNOW™を用いた検査でも陰性証明として使用されています。
PCR検査の原理
PCR検査とNEAR法による検査を理解するには、遺伝子について理解しないといけません。
全ての生物の遺伝子はDNAとして保存されます(ウイルスはRNAです)。
DNAは、2つの鎖がつながるように記録されています。
遺伝子とは、DNAの中の特定の機能をもった一部分のことです。
例えばウイルス特有の遺伝子があるかを見るには、
遺伝子を目で見るわけにいかないのでウイルス特有の遺伝子を増やして
人間の目にもわかるようにしてあげる必要があります。
そこで、PCR検査では、
- 温度を上げると、DNAが1本ずつに分かれるのを利用して、温度を上げて1本ずつにします。
長いDNAであるほど、高い温度が必要になります。
- ウイルス特有の遺伝子がわかる標識(プライマー)をつけます。
標識をつけられると、プライマーの部分から先の部分だけ、DNAが増幅されるようになります。
- 特殊な酵素を用いて、もう片方のDNAを伸ばしていきます。両端を認識する必要があるので、
プライマーは2種類必要ということになります。
- 急速に冷凍します。急速に冷凍するほど、長いDNAは結合しにくいですが、
短いDNAは結合しやすくなります。両端にプライマーが付けられ短くなった
- ウイルス特有の遺伝子だけは、短いDNAになっているので、増幅しやすい環境になります。
このように、温度を上げ下げすることで目的となる遺伝情報を増やしていくのが「PCR法」です。
(本当はウイルスはRNAなので、最初特殊な酵素を使ってDNAに変換しています)
非常に簡便であり、機械が自動でやってくれるので、人の手は最小限になります。
また、各設定温度や時間を変えることで、様々な長さの「遺伝情報」にも対応できるのが特徴です。
しかし、温度を上げ下げしないといけない分、時間がかかります。
それを解決する方法がNEAR法でも見られる「等温核酸増幅法」で
温度を上げ下げしないでも遺伝情報を増幅できる方法になります。
IDNOW™による「NEAR法」と「PCR法」の違いは?
上記を踏まえると、NEAR法とPCR法の違いは次の通りです。
- NEAR法の方が素早くできる: NEAR法は等温核酸増幅法の1つで、
温度を上げ下げせずに遺伝情報を増幅するので、時間が短縮されるのが特徴です。
- NEAR法は短い遺伝情報をターゲットにするのに向いている:NEAR法の原理上、
ターゲットとなる遺伝情報のサイズが(<100nt)と短くなります。
NEAR法を一言でいうと「短い遺伝情報をPCRよりも大量に作る」のが特徴です。
IDNOW™の遺伝子検査では「ウイルスに特有の遺伝情報」を、短い領域に絞って増幅することで、
さらに短時間に人間の目にも見えるようにしたものといえます。
そのため行っていることは「遺伝情報の増幅」であり、PCR法と原理上もほぼ同等といえるのです。
IDNOW™による新型コロナ感染症遺伝子検査の精度は?
では IDNOW™による新型コロナ感染症遺伝子検査 の精度はどれくらいでしょうか。
米国応急診療所(アージェント・ケア)5カ所で行われた計256例の検査結果では、PCR検査と比較して
陽性一致率94.7%、陰性一致率98.6%でした。
お互い手技上のエラーなども考えると、非常に高い精度だといえます。(Abott社HPによる)
また、臨床性能試験成績では、新型コロナ患者からの議事陽性検体30検体と陰性検体30検体で、
すべて陽性陰性を正確に判別できています(IDNOW™添付文書による)。
また、英国型変異株や南アフリカ変異株などの変異株に対しても、
検査の精度に影響がないことが確認されています。
実際それを受けてアメリカ(ハワイ含む)や韓国などでは、
「IDNOW™の陰性結果で海外渡航における陰性証明としてよい」としており、
非常に高い信頼性であることがうかがえるでしょう。(2021年11月現在)
IDNOW™による新型コロナ感染症遺伝子検査の費用
IDNOW™による新型コロナ感染 遺伝子検査の費用は次の通りです。
| 症状のある場合・濃厚接触者 |
無料(公費でうけることが
できます) |
| 症状のない場合 |
11000円(診察料・税込) |
* 症状のある場合は、事前連絡の上、発熱外来の受診をお願いします。
* 症状のない場合、電話予約にて検査を受けつけます。
自費の場合のIDNOW™検査の流れ
「IDNOWによる遺伝子検査を行いたい」という場合の流れとしては以下の通りとなります。
- 当院電話連絡にて日時を決定します。(検査時間は午前10時~12時と午後3時~5時になります)
- 来院後、遺伝子検査に関する同意書に記載していただきます。
- 遺伝子検査を行います: 鼻の奥から検体を採取します。
結果は検査当日にお渡しするか、後日お渡しになります。
もし陽性であった場合は、現時点では保健所への連絡を行い、指示に従っていただくことになります。
2021-07-09
現在、当院でも新型コロナウイルスワクチンの接種を行っています。
新型コロナウイルスワクチン接種後の発熱などについては、市販の解熱鎮痛薬で
対応することも考えられるとし、厚労省はウェブサイト上で解熱鎮痛薬の
具体的な種類を提示しています。ワクチン接種の広がりとともに、接種後の発熱や
痛みなどに備えて薬局などで購入できるアセトアミノフェン含有OTC薬の需要が急増しており、
一部品薄になっている製品もあります。
薬局やドラッグストアなどにおいて正確な情報提供が求められています。
なお、ワクチン接種後、症状が現れる前に解熱鎮痛薬を予防的に繰り返し内服することは、
現状では推奨されていません。
ワクチン接種にあたっては
(1)他の薬を内服している場合や、妊娠中・授乳中、高齢者、胃・十二指腸潰瘍や腎機能低下などで治療している
(2)薬などでアレルギー症状や喘息を起こしたことがある
(3)激しい痛みや高熱など症状が重い、または症状が長く続いている
(4)ワクチン接種後としては典型的でない症状が見られる
上記のような場合には、主治医や薬剤師に相談するよう求めています。
当院では接種前に問診を行っておりますが、その際に何かわからなければ
質問ください。
« Older Entries